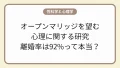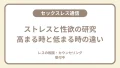男性から一度でも嫌われたら、もう二度と好きになってもらえないのでしょうか?
これは相手のタイプによって異なります。
判断するためには「対人スキーマ」を確認しましょう。
対人スキーマとはなにか?
人間は相手の言動から、性格や自分に対して向けている感情を判断します。
この判断のための型(フレーム)を「対人スキーマ」といいます。
相手の笑顔を見たとき「好意」と受け取る人もいれば、「バカにされた」と受け取る人もいるのは、この対人スキーマに個人差があるからです。
対人スキーマは「思い込みの型」ともいえます。
「私の意見に反対するのは、私のことが嫌いだからだ」と思い込む人は、否定的な対人スキーマを持っているといえます。
対人スキーマは親の育て方や、これまでに体験した人間関係から様々なパターンを学ぶことで形成されていきます。
嫌いになった相手を好きにならない人
対人スキーマによって作られた相手への印象が後で変化するかどうかにも個人差があります。
一度つくられた印象が変わらない人は、硬直性の高い対人スキーマを持っているといえます。
そして、このタイプは相手のことを一度でも嫌いと思ったら、その後に相手が好意的な態度を示し続けても好きになることはありません。
相手の全ての言動を否定的な心のレンズを通してしか見られなくなってしまっているからです。
一度嫌いになったら変わらない人の特徴
もし、あなたの好きな男性が硬直性の高い対人スキーマを持っていた場合、一度でも嫌われてしまったら後で好きになってもらうのは難しいといえます。
では、どのようにそれを見分ければ良いのでしょうか?
過去の心理学の研究によって、硬直性の高い対人スキーマを持つ人には、以下のような特徴があることが分かっています。
【特徴1】二分法的な思考を持っている
物事を理解するときに両極端に決めつけてしまうことを「二分法的な思考」といいます。「白黒思考」や「全か無か思考」などと呼ばれたりもします。
たとえば、仕事でちょっとミスをしただけで「全て失敗だ」と考えてしまうようなことです。
対人関係においても「敵か味方か」といった極端な見方をしがちで、「悪いところもあるけれど、良いところもある」といった中間的な見方ができないのです。
こうした二分法的な思考は硬直性の高い対人スキーマを持っていることの表れといえます。
【特徴2】自己確信が強い
自己確信(Self-certainty)とは、自分が下した判断や思考に対して、どの程度「確かだ」と感じているかを示すものです。
これは「自信」とは少し異なり、「自分の考え方は間違っていない」「自分の見方は正しいはずだ」といった思い込みの強さを意味します。
テストで答えを書いたあとに「これは絶対に正解だ」と強く信じ込む人は自己確信が強いといえます。
自己確信が強いと、自分の考えに固執してしまい、新たな事実が出て来てもそれを受け入れ難くなります。そのため、一度「嫌い」という印象を持ったらそれを変えられないのです。
【特徴3】不確実性への受容が低い
不確実性への受容(Tolerance of uncertainty)とは、はっきりしない状況や先が読めない出来事に対して、どの程度受け入れられるかを示す概念です。
たとえば、相手から返信が来ないとき、「忙しいのだろう、しばらく待ってみよう」と考えられる人は不確実性への受容が高いといえます。
逆に、不確実性への受容が低い人は、少しの曖昧さや予測不能な状況でも強い不安やストレスを感じやすく、「すぐに答えを知りたい」「はっきりさせないと気がすまない」となりがちす。
その結果、柔軟な対応が難しくなり、一度決めた判断を覆さなくなるのです。
また、このタイプは日常生活でのストレスを感じやすいため、些細なことで相手を嫌うこともあります。
硬直性の高い対人スキーマを持つ人に好きになってもらえるか
上記の特徴を持つ人は、硬直性の高い対人スキーマを持っている可能性が高いですから、一度でも嫌われてしまったら好きになってもらうどころか、関係を修復することさえ難しくなります。
ではこの対人スキーマの硬直性は変化するものなのでしょうか?
結論からいうと、その可能性は低いといえます。
対人スキーマというのは、科学的な言い方をするなら「どの感情を生じさせる脳内の神経細胞がつながりやすいのか?」ということです。
一度嫌いになった相手をずっと嫌いな人というのは、相手の言動を受け取ったときに脳内で「嫌い」という感情を生じさせる神経細胞がつながりやすく、そこが変化しにくいネットワークを持っているということです。
これを変えるためには認知行動療法などの専門的なトレーニングを繰り返すことで、脳内のネットワークの繋がり方を変化させる必要があります。
ですから、本人が「変わりたい」という意思をもって主体的に行動しない限りは難しいのです。
もちろん日常生活の中で転機となるような出来事に遭遇したり、影響力の強い人との出会いの中で、変化することもあり得ますが、その可能性はかなり低いといえます。
一度嫌われたら終わりどころか復讐されるパターン
当方に相談に来ている女性から、次のようなエピソードを聞くことがあります。
- 元カレが「嫌い」と言って別れたのに連絡してくる
- LINEを既読無視してたのに急に遊びに誘ってくる
このようなパターンでは、相手の男性が単に優柔不断だったり、駆け引きをしているだけなら脈アリの可能性もあるでしょう。
しかし、ダークトライアドと呼ばれる性格の持ち主だった場合には、かなり危険な状況といえます。
ダークトライアドとは
ダークトライアドとは下記の3つの邪悪な性格傾向の総称です。
- マキャベリズム:目的のために他者を操作し、策略的に行動する傾向
- ナルシシズム:過度に自己を誇示し、賞賛や特別扱いを強く求める傾向
- サイコパシー:共感性や罪悪感に乏しく、衝動的かつ反社会的に振る舞う傾向
これらの性格傾向を持つ男性の場合、復讐や快楽のために自分に恋愛感情を持つ相手を弄ぶことがあります。
そしてそのことに罪悪感を持ちませんから行為がよりエスカレートすることもあり、巻き込まれると精神的に疲弊します。
ダークトライアドも硬直性の高い対人スキーマを持っている
また、このダークトライアド傾向を持つ人も、ここまで説明した硬直性の高い対人スキーマを持っていることも分かっています。
つまり、一度嫌いになったら好きになることはないということです。それどころか「俺に敵意を向けたアイツを痛めつけてやる」と考えている可能性さえあるのです。
ダークトライアドは全人口の1~3%はいるとされており、先天的な脳の特徴であるため変わる可能性は非常に低いといえます。
相手の思わせぶりな態度を見て「もしかしてまた好きになってくれたのかも」などと勘違いしないようにしましょう。
<参考文献>
・Baldwin, M. W. (1992). Relational schemas and the processing of social information.
・Boban N, Bojana D, Luna T. 2025. The dark triad and forgiveness: The mediating role of anger rumination.